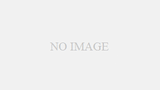目次
<特発性血小板減少性紫斑病>はどんな病気?
<特発性血小板減少性紫斑病(ITP)>とは?
🔹 基本的な特徴
- 正式名称:免疫性血小板減少性紫斑病(Idiopathic / Immune Thrombocytopenic Purpura, ITP)
- 自己免疫によって血小板が壊され、さらに骨髄での血小板産生も抑えられることで、血小板が減少する病気です。
- 血小板は血を固める役割があるため、数が減ると 出血しやすくなる。
🔹 主な症状
- 皮膚の出血斑(紫斑):青あざのような点状出血や斑状出血。
- 鼻血、歯ぐき出血。
- 女性では月経過多。
- 重症では消化管出血、脳出血など致命的な出血に至ることもある。
🔹 原因
- 免疫の異常で、自分の血小板に対する自己抗体が作られる。
- その結果、脾臓などで血小板が壊されやすくなる。
- 多くは 原因不明(特発性) だが、ウイルス感染やワクチン接種後などをきっかけに発症することもある。
🔹 診断
- 血液検査:血小板が低値。
- 骨髄検査:血小板をつくる巨核球は存在する(=産生能は保たれている)。
- 他の血小板減少を起こす病気(白血病、再生不良性貧血、膠原病など)を除外して診断。
🔹 経過のタイプ
- 急性型:小児に多く、ウイルス感染後に発症。数週間〜数か月で自然に治ることが多い。
- 慢性型:成人に多く、6か月以上持続。自然治癒は少なく、治療を続ける必要がある場合が多い。
✅ まとめ
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)は、免疫の異常で血小板が壊されて減る病気で、
症状は 紫斑・鼻血・歯ぐき出血・月経過多などの出血症状。
小児は急性型が多く自然治癒しやすく、成人は慢性型が多いのが特徴です。
<特発性血小板減少性紫斑病>の人はどれくらい?
<特発性血小板減少性紫斑病(ITP)>は まれな自己免疫疾患 ですが、世界的に一定の患者数が報告されています。
🔹 発症頻度(罹患率)
- 年間発症率:人口100万人あたり 2〜4人程度。
- 有病率(患者が存在している割合):人口10万人あたり 10〜20人程度。
- つまり、10万人に1〜2人がI TPで治療中とされます。
🔹 日本での患者数
- 厚生労働省の「指定難病」データによると、
- 登録患者数は 約2万人前後 とされています。
- 実際の潜在患者を含めると、さらに多いと推定されます。
🔹 年齢・性別の特徴
- 小児:一時的に発症する「急性型」が多い。多くは数か月で自然回復。
- 成人:特に 中年以降の女性 に多い。慢性化しやすく、長期的な治療が必要になることもある。
- 男女比 → 成人では女性が男性の約2倍。
✅ まとめ
- 発症率は 年間100万人あたり2〜4人。
- 日本では 約2万人程度の患者さん が登録されている。
- 小児は急性型、成人は慢性型 が多い。
- 成人女性に多く、長期経過をたどるケースが多い。
<特発性血小板減少性紫斑病>の原因は?
<特発性血小板減少性紫斑病(ITP)>の原因は、「自分の免疫が血小板を攻撃してしまうこと」です。
🔹 ITPの原因・発症のしくみ
1. 自己免疫による血小板破壊
- 免疫の異常で 自己抗体(IgG型が多い) が作られ、血小板表面の膜糖タンパク(GPIIb/IIIa、GPIb/IXなど)に結合。
- 抗体がついた血小板は、脾臓・肝臓のマクロファージに食べられて減少。
2. 血小板産生の低下
- 骨髄の巨核球(血小板を作る細胞)にも抗体やT細胞が作用して、血小板の産生自体も低下する。
- つまり「壊されるのが増える+作られるのが減る」の両方が関与。
3. 発症のきっかけ(誘因)
- 多くは「特発性=はっきりした原因なし」とされるが、次のようなことが引き金になることがあります。
- ウイルス感染(かぜ、EBウイルス、HIV、C型肝炎など)
- ワクチン接種後(MMR、水痘、COVID-19などで報告例あり)
- 薬剤(抗生物質、抗てんかん薬など)
- 妊娠(妊娠関連ITPとして出現)
4. 遺伝との関わり
- 基本的に「遺伝病」ではなく、家族に同じ病気が出ることはまれ。
- ただし免疫の体質的な違い(HLAタイプなど)が発症に関与している可能性はあります。
✅ まとめ
- ITPは 免疫の異常で血小板に抗体がつき、脾臓で壊される病気。
- 骨髄での産生低下も関与。
- 多くは原因不明だが、感染・ワクチン・薬剤・妊娠 などがきっかけになることがある。
- 遺伝性は基本的にありません。
<特発性血小板減少性紫斑病>は遺伝する?
<特発性血小板減少性紫斑病(ITP)>は基本的に遺伝しません。
🔹 遺伝するかどうか
1. 遺伝しない理由
- ITPは 後天性の自己免疫疾患 です。
- 免疫システムが誤って「自分の血小板」を敵と認識して抗体を作ることで起こります。
- 遺伝子の異常で直接起きる病気ではないため、親から子へそのまま受け継がれることはありません。
2. 家族で発症することがある?
- ごくまれに家族内で複数人にITPがみられることはありますが、これは「遺伝性疾患」というより 免疫の体質や環境要因が重なった偶然 と考えられます。
- 直接的に「子どもに必ず遺伝する」という病気ではありません。
3. 遺伝性と区別が必要な病気
- 遺伝性血小板減少症(例:Bernard-Soulier症候群、Wiskott-Aldrich症候群など)
→ これらは遺伝子異常が原因で血小板が減るため「先天性」であり、ITPとは別の病気です。 - ITPと誤診されることもあるので、若年発症や家族歴がある場合は遺伝性の病気との鑑別が必要。
✅ まとめ
- ITPは遺伝しない。
- 家族に出ても「遺伝」というより体質や環境要因が関係している。
- ただし「先天性血小板減少症」という遺伝病は別にあり、ITPと区別して考える必要がある。
<特発性血小板減少性紫斑病>の経過は?
🔹 経過の全体像
ITPは 血小板が少ない状態がどのくらい続くか によって経過が分かれます。
- 急性型
- 主に小児に多い。
- かぜなどウイルス感染をきっかけに発症。
- 数週間〜数か月で自然に血小板数が回復することが多い。
- 6か月以内に改善すれば「急性型」と呼ぶ。
- 慢性型
- 成人に多い。
- 6か月以上血小板減少が続く場合。
- 自然治癒は少なく、長期にわたって経過観察や治療が必要になることもある。
🔹 症状の進行
- 軽症:紫斑や点状出血だけ。血小板が3〜5万/μL程度なら、日常生活で大きな支障は少ない。
- 中等症:血小板が2万/μL以下になると、鼻血や歯ぐき出血、月経過多など出血症状が増える。
- 重症:1万/μL以下では消化管出血、尿路出血、まれに脳出血など生命に関わる出血が起こることもある。
🔹 長期的な経過
- 小児急性型 → 多くは自然寛解。
- 成人慢性型 → 完全に治ることは少なく、
- ステロイドや免疫抑制剤でコントロール
- 長期に低い血小板数でも出血が少なければ経過観察のみ
- 一部は治療抵抗性(難治性ITP)となり、脾摘や新しい分子標的薬(トロンボポエチン受容体作動薬など)が必要になる。
🔹 予後
- 小児ITP:良好。数か月で改善することが多い。
- 成人ITP:慢性化しやすいが、致命的な出血はまれ。
- 最近は治療薬の進歩(トロンボポエチン受容体作動薬など)により、難治例の予後も改善している。
✅ まとめ
- ITPは「小児は急性で自然回復しやすい」「成人は慢性で長期管理が必要」なのが特徴。
- 血小板数が極端に減ると重症出血リスクがあり、治療や生活管理が欠かせない。
- 生命予後は全体としては比較的良好だが、慢性化や難治化への注意が必要。
<特発性血小板減少性紫斑病>の治療法は?
🔹 治療の基本方針
- ITPは「血小板が減る病気」ですが、すべての人にすぐ治療が必要なわけではありません。
- 血小板数が 3万/μL以上 で出血が少なければ、経過観察のみの場合もあります。
- 出血リスクが高いとき(血小板数が少ない、出血症状が強い)は治療を行います。
🔹 主な治療法
1. 急性期の治療
- 副腎皮質ステロイド(プレドニゾロンなど)
→ 第一選択。免疫を抑えて血小板破壊を減らす。 - 免疫グロブリン大量静注(IVIG)
→ 緊急時(出血が強い場合や手術前)に短期間で血小板を増やす。 - 抗D免疫グロブリン(Rh陽性患者に限る)
→ 日本ではあまり使われませんが、血小板破壊を抑制。
2. 慢性期・再発例の治療
- 脾臓摘出(脾摘)
→ 脾臓で血小板が壊されるのを防ぐ。成人慢性例で効果が高く、約6〜7割で長期寛解。 - 免疫抑制薬(シクロスポリン、アザチオプリンなど)
→ ステロイドや脾摘が効かない場合に使用。
3. 分子標的治療(新しい薬)
近年は「血小板をつくる力を高める薬」が普及しています。
- トロンボポエチン受容体作動薬(TPO-RA)
- エルトロンボパグ(経口)
- ロミプロスチム(皮下注射)
→ 骨髄の巨核球を刺激し、血小板を増やす。慢性ITPで広く使われる。
4. その他の選択肢
- リツキシマブ(抗CD20抗体)
→ B細胞を減らし、自己抗体産生を抑える。再発・難治例で使われる。 - フォスタマチニブ(脾臓マクロファージでのFc受容体シグナル阻害薬)
→ 海外で承認済、日本ではまだ限定的。
🔹 小児と成人の違い
- 小児:多くは自然に治るので、出血が軽ければ観察のみ。必要時はIVIG。
- 成人:慢性化しやすく、薬物療法や脾摘、TPO-RAなど長期的管理が中心。
✅ まとめ
- 治療開始は「出血リスクの有無」で決定。
- 第一選択:ステロイド。重症例ではIVIGを併用。
- 慢性・再発例:脾摘、免疫抑制薬、リツキシマブ、TPO-RA。
- 小児は経過観察が多く、成人は慢性管理が中心。
<特発性血小板減少性紫斑病>の日常生活の注意点
🏡 日常生活での注意点
1. 出血を防ぐ工夫
- ケガを避ける生活
- 接触や転倒のリスクがあるスポーツ(格闘技、サッカー、スキーなど)は控える。
- 家の中でも転倒防止(カーペットや段差に注意)。
- 口腔ケア
- 歯ブラシはやわらかめを使用。歯ぐきからの出血に注意。
- 内出血に注意
- 打撲・青あざが増えたら早めに受診。
- 薬の注意
- アスピリンやNSAIDs(解熱鎮痛薬)は血小板機能を下げて出血リスクを高めるため、主治医に確認してから使用。
2. 感染予防(治療中の免疫抑制対策)
- ステロイドや免疫抑制薬を使っている場合は感染に弱くなる。
- 手洗い・うがい・マスクを徹底。
- 人混みや風邪が流行している場所は避ける。
- 必要に応じて ワクチン接種(インフルエンザ・肺炎球菌など) を検討。
3. 食生活
- 特別な制限はないが、アルコールは控えめに。肝機能を悪化させると血小板減少が悪化することもある。
- バランスの良い食事を心がけ、免疫力を保つ。
- サプリメントは薬との相互作用があることがあるため、使用前に医師に相談。
4. 女性の場合(月経・妊娠)
- 月経過多が出やすい → 出血量が多い場合は主治医に相談(ホルモン療法や止血薬を使うこともある)。
- 妊娠は可能だが、出産時の出血リスクがあるため妊娠前から主治医と相談し、周産期管理を行う。
5. 定期受診と自己管理
- 血小板数の定期チェックが必要。
- 体調記録:あざ・出血・鼻血の頻度をメモして診察時に伝えると有用。
- 新しい症状(頭痛、視覚異常、黒色便など)があればすぐに医師に連絡(脳出血・消化管出血の可能性)。
✅ まとめ
- 出血を防ぐ生活習慣(ケガ予防・薬剤注意)。
- 感染予防(手洗い・マスク・ワクチン)。
- 食生活は基本自由だがアルコール控えめ。
- 女性は月経・妊娠での出血管理が重要。
- 定期受診と体調記録で自己管理。