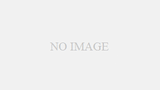目次
<再生不良性貧血>はどんな病気?
再生不良性貧血(aplastic anemia) は、骨髄がうまく血液をつくれなくなる病気です。
- 🔹 基本的な特徴
- 🔹 主な症状
- 🔹 原因
- 🔹 診断
- 🔹 治療
- ✅ まとめ
- 🔹 世界全体の発症頻度
- 🔹 日本でのデータ
- 🔹 年齢分布
- ✅ まとめ
- 1. 特発性(原因不明)
- 2. 二次性(何らかの外的要因が関与)
- 1. 大多数(後天性・特発性)
- 2. 遺伝性のタイプ(まれ)
- 🔹 再生不良性貧血の経過
- 1. 初期〜診断時
- 2. 症状の進行
- 3. 治療による分岐
- 4. 長期経過での問題
- 5. 予後
- 1. 支持療法(症状を和らげる治療)
- 2. 根治をめざす治療
- 3. 薬物治療(免疫抑制療法)
- 4. 遺伝性の場合(ファンコニ貧血など)
- 1. 貧血(赤血球が少ない)への対応
- 2. 感染(白血球が少ない)への対応
- 3. 出血(血小板が少ない)への対応
- 4. 食生活
- 5. 仕事・学校・妊娠
- 6. 精神的サポート
🔹 基本的な特徴
- 骨髄の造血幹細胞(血液をつくるもとになる細胞)が減少・機能低下する。
- そのため 赤血球・白血球・血小板がすべて不足(=汎血球減少)する。
- 骨髄は「低形成骨髄」と呼ばれ、細胞が少なく脂肪で置き換わっていることが多い。
🔹 主な症状
血球が減ることで以下の症状が出ます:
- 赤血球減少 → 貧血(息切れ、動悸、顔色不良、疲れやすさ)
- 白血球減少 → 感染症にかかりやすくなる
- 血小板減少 → 出血傾向(歯ぐき出血、皮下出血、鼻血、月経過多 など)
🔹 原因
- 多くは 自己免疫による造血幹細胞への攻撃(特発性)。
- 他にも:薬剤(抗がん剤・抗菌薬など)、放射線、ウイルス感染(B型肝炎など)、ベンゼンなど化学物質、遺伝性(ファンコニ貧血など)。
🔹 診断
- 血液検査で 汎血球減少。
- 骨髄穿刺で 低形成骨髄(造血細胞が少ない) を確認。
- 他の疾患(白血病・骨髄異形成症候群など)との鑑別が必要。
🔹 治療
- 軽症〜中等症 → 薬物治療(免疫抑制療法:シクロスポリン、抗胸腺細胞グロブリン〈ATG〉)。
- 重症例
- 若年者:造血幹細胞移植(同種骨髄移植)。
- 高齢者や移植不適応例:免疫抑制療法+支持療法(輸血、G-CSFなど)。
- 支持療法:赤血球輸血、血小板輸血、感染予防。
✅ まとめ
再生不良性貧血は、骨髄の造血機能が低下して すべての血球が減少する病気。
症状は「貧血・感染・出血」が三本柱で、治療は 免疫抑制療法や骨髄移植 が中心です。
<再生不良性貧血>の人はどれくらい?
再生不良性貧血の患者さんの数(有病率・発症率) は地域によって差があります。
🔹 世界全体の発症頻度
- 年間発症率は 人口100万人あたり2人前後 とされるまれな病気。
- ただし 東アジア(中国・日本)ではやや多く、人口100万人あたり5〜7人程度 と報告されています。
- 欧米に比べてアジアで発症率が高いのが特徴です。
🔹 日本でのデータ
- 日本の厚生労働省の難病指定疾患(指定難病)に含まれており、患者数の登録があります。
- 2020年代のデータでは、全国で約6,000〜7,000人程度の患者さん が医療費助成の対象として登録されています。
- 毎年 数百人程度の新規患者 が発生していると考えられています。
🔹 年齢分布
- 二峰性分布を示すのが特徴。
- 10〜20歳の若年者に多いピーク。
- 60歳以上の高齢者にもう一つのピーク。
✅ まとめ
- 再生不良性貧血は まれな病気(人口100万人あたり年間2〜7人程度)。
- 日本では 患者数は約6,000〜7,000人。
- 若年者と高齢者の二峰性に発症が多い。
<再生不良性貧血>の原因は?
🔹 再生不良性貧血の原因
1. 特発性(原因不明)
- 全体の 70〜80% を占める。
- 近年の研究では「自己免疫が造血幹細胞を攻撃して壊す」ことが主な仕組みと考えられている。
- Tリンパ球が活性化して幹細胞を傷つける。
- インターフェロンγやTNF-αといった炎症性サイトカインが関与。
2. 二次性(何らかの外的要因が関与)
(1)薬剤
- 抗がん剤(アルキル化薬など)、クロラムフェニコール(古い抗菌薬)、抗リウマチ薬、抗てんかん薬など。
(2)放射線・化学物質
- 放射線被曝。
- ベンゼン(有機溶剤)など造血幹細胞毒性のある化学物質。
(3)感染症
- 一部のウイルス感染(B型肝炎、EBウイルス、パルボウイルスB19など)後に発症することがある。
- 「肝炎後再生不良性貧血」と呼ばれるタイプもある。
(4)自己免疫疾患・免疫異常
- 全身性エリテマトーデス(SLE)などの自己免疫疾患に合併することがある。
(5)遺伝性疾患
- ファンコニ貧血:DNA修復異常を持つ先天性疾患。若年発症。
- 先天性角化異常症など。
🔹 日本人に多い原因の特徴
- 多くは 特発性(免疫性)。
- 「肝炎後発症」のタイプはアジアに比較的多い。
- 薬剤性やベンゼン曝露によるものは、現在はまれ。
✅ まとめ
- 再生不良性貧血は 造血幹細胞が壊されて血液がつくれなくなる病気。
- 大部分は特発性(自己免疫性)。
- その他、薬剤・放射線・化学物質・感染症・遺伝性疾患が原因になる。
- 日本では 特発性と肝炎後発症型 が目立つ。
<再生不良性貧血>は遺伝する?
<再生不良性貧血>は基本的に「遺伝しない」病気ですが、例外的に遺伝性のタイプもあります。
🔹 遺伝するかどうか
1. 大多数(後天性・特発性)
- 日本人を含め、成人や若年者に見られる多くの再生不良性貧血は 後天性(獲得性)。
- 自己免疫によって骨髄の造血幹細胞が破壊されるのが主な原因で、 遺伝はしません。
- 家族内発症は基本的にみられません。
2. 遺伝性のタイプ(まれ)
一部の「先天性再生不良性貧血」は遺伝します。
- ファンコニ貧血
- DNA修復異常が原因の先天性疾患。
- 常染色体劣性遺伝。
- 発育障害や奇形を伴うことが多い。
- 先天性角化異常症(Dyskeratosis congenita)
- テロメア維持機構の異常。
- 遺伝形式は常染色体劣性・優性やX連鎖など多様。
- 皮膚・爪・粘膜の異常も特徴的。
- シャフマン・ダイアモンド症候群(Shwachman-Diamond syndrome)
- 膵外分泌不全や骨格異常を伴う。
👉 これらは全体のごく一部で、臨床現場で遭遇する再生不良性貧血のほとんどは 遺伝しない後天性 です。
✅ まとめ
- 一般的な再生不良性貧血は遺伝しない。
- ただし、ファンコニ貧血や先天性角化異常症など一部の先天性タイプは遺伝性。
- 遺伝性かどうかは、発症年齢、合併症、家族歴、遺伝子検査で判断されます。
<再生不良性貧血>の経過は?
🔹 再生不良性貧血の経過
1. 初期〜診断時
- 発症はゆっくり進行することも、急に汎血球減少が目立って診断されることもある。
- 最初は 軽い貧血や皮下出血 で気づかれる場合が多い。
2. 症状の進行
- 赤血球減少 → 貧血症状(息切れ・動悸・倦怠感) が進行。
- 白血球減少 → 感染症にかかりやすくなる(肺炎、敗血症が重篤化しやすい)。
- 血小板減少 → 出血傾向(鼻血、歯ぐき出血、皮下出血、月経過多、消化管出血など) が増える。
- 病状の進行速度は人により大きく異なる。
3. 治療による分岐
- 免疫抑制療法(ATG+シクロスポリンなど)
→ 有効例では数か月〜1年で造血が回復し、輸血不要になりうる。
→ ただし再発や部分寛解も多い。 - 造血幹細胞移植
→ 成功すれば根治が期待できる。
→ 拒絶反応や移植後合併症のリスクあり。
4. 長期経過での問題
- 再発:免疫抑制療法後に数年で再び汎血球減少が起こることがある。
- クローン性造血の出現
- 骨髄異形成症候群(MDS)や急性骨髄性白血病(AML)への移行が、一部で見られる。
- PNH(発作性夜間ヘモグロビン尿症)のクローンが生じることもある。
- 支持療法による合併症:輸血を繰り返すことで鉄過剰症(心・肝障害のリスク)が起こる。
5. 予後
- 治療法の進歩により、生存率は大きく改善。
- 造血幹細胞移植が適応できれば、長期生存率は70〜80%以上。
- 免疫抑制療法でも有効例では10年以上の生存が可能。
- ただし、高齢者や治療抵抗例では感染や出血死のリスクが依然として高い。
✅ まとめ
- 経過は「徐々に進行する血球減少 → 感染・出血・貧血の症状 → 治療によって改善 or 再発・合併症へ」という流れ。
- 治療が有効なら長期生存が可能だが、再発・クローン性疾患(MDS/AML/PNH)への移行が長期的な課題。
- 予後は治療法の発展で改善しつつあるが、年齢や全身状態によって左右される。
<再生不良性貧血>の治療法は?
<再生不良性貧血>の治療法は「骨髄の造血が止まっている状態をどう回復させるか」がポイントで、年齢・重症度・ドナーの有無によって大きく変わります。
🔹 再生不良性貧血の治療法
1. 支持療法(症状を和らげる治療)
- 輸血
- 赤血球輸血:貧血の改善。
- 血小板輸血:出血予防。
- 感染予防
- 抗菌薬・抗真菌薬・抗ウイルス薬の使用。
- 無菌室管理が必要な場合もある。
- 鉄過剰症対策
- 輸血が長期になると鉄が体にたまる → 鉄キレート薬(デフェラシロクなど)で除去。
2. 根治をめざす治療
(1)造血幹細胞移植(骨髄移植)
- 第一選択となるのは若年者(40歳前後まで)で、HLAが一致する兄弟姉妹ドナーがいる場合。
- 成功すれば根治が期待できる。
- 移植後は拒絶反応や感染のリスクがあるため注意が必要。
3. 薬物治療(免疫抑制療法)
骨髄を攻撃している免疫反応を抑える目的。
- 抗胸腺細胞グロブリン(ATG)+シクロスポリン(CsA)
- 世界的に標準的な治療。
- 数か月〜半年で造血回復が見られることも多い。
- エルトロンボパグ(トロンボポエチン受容体作動薬)
- 骨髄を刺激して造血を促す新しい薬。
- ATG+CsAと併用すると奏効率が上がることが報告されている。
- 副腎皮質ステロイド
- 主にATGの副作用対策として使用。
4. 遺伝性の場合(ファンコニ貧血など)
- 移植が根治的治療になるが、通常より毒性に弱いため前処置を弱めた移植法が用いられる。
🔹 治療方針のまとめ
- 若年者+適合ドナーあり → 造血幹細胞移植(根治をめざす)。
- 高齢者 or ドナー不適合 → 免疫抑制療法(ATG+CsA±エルトロンボパグ)。
- 全員に必要 → 支持療法(輸血・感染予防・鉄過剰対策)。
✅ まとめ
- 再生不良性貧血は「支持療法+根治療法」の組み合わせ。
- 若い人は骨髄移植が第一選択、移植できない人は免疫抑制療法が中心。
- 新薬(エルトロンボパグ)によって治療成績は改善しつつある。
<再生不良性貧血>の日常生活の注意点
<再生不良性貧血>の日常生活の注意点を「血球減少ごとのリスク」に分けて整理しますね。
🏡 日常生活での注意点
1. 貧血(赤血球が少ない)への対応
- 無理な運動を避ける:息切れ・動悸が出やすいので、疲れすぎない範囲で。
- 立ちくらみ・めまいに注意し、転倒しやすい環境(段差、急な動き)は避ける。
- 適度な休養と十分な睡眠をとる。
2. 感染(白血球が少ない)への対応
- 手洗い・うがい・マスクを徹底。人混みや風邪流行時の外出は控える。
- **生もの・非加熱食品(刺身・生卵・生肉など)**は感染リスクがあるため避ける。
- ワクチン接種(インフルエンザ・肺炎球菌など)は主治医と相談のうえで検討。
- 発熱(37.5℃以上)が出たらすぐに医療機関へ。感染は重症化しやすい。
3. 出血(血小板が少ない)への対応
- 歯ブラシは柔らかい毛を使用し、歯ぐきの出血に注意。
- **打撲・ケガをしやすいスポーツ(サッカー、格闘技など)**は避ける。
- 鼻を強くかまない・転倒しないよう注意。
- 出血が続くときはすぐ受診。
4. 食生活
- 特別な食事制限はないが、鉄過剰症がある人は鉄分サプリを避ける。
- 栄養バランスを意識して体力維持。
- アルコールは肝機能に負担をかけ、薬の効果に影響する可能性があるため控えめに。
5. 仕事・学校・妊娠
- 体調に合わせて無理のないペースで復帰。感染リスクが高い職場(保育園、医療現場など)では特に注意。
- 妊娠は病状が安定していれば可能なこともあるが、母体・胎児双方にリスクが高いため必ず主治医と相談。
6. 精神的サポート
- 長期治療や入院でストレスが強くなるため、家族や医療スタッフとの相談・カウンセリングが大切。
✅ まとめ
- 感染予防・出血予防・疲労回避が生活の柱。
- 「手洗い・マスク・人混み回避」「ケガをしない工夫」「休養をとる」ことが基本。
- 栄養・睡眠・精神的ケアも含めて、日常を安定させることが大切。