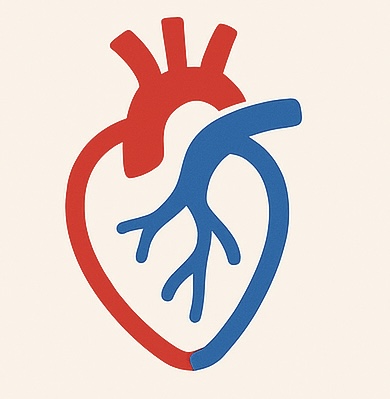目次
<膿疱性乾癬(汎発型)>はどんな病気?
<膿疱性乾癬(汎発型)>は、
皮膚の広範囲に無菌性(細菌感染がない)膿疱が急激に出現し、全身症状を伴うことがある重症型の乾癬です。
特徴
- 急激な発症:数時間~数日のうちに皮疹が広がる
- 膿疱:皮膚が赤くなった上に小さな白い膿のう(膿疱)が多数出現
- 全身症状:高熱、倦怠感、悪寒、関節痛など
- 再発しやすい:症状が改善しても、再び発症することがある
発症メカニズム
- 免疫異常により、皮膚の炎症反応が過剰に活性化され、好中球が皮膚表面に集まり膿疱を形成
- 感染は伴わないが、炎症が全身に影響しうる
代表的な誘因
- 感染症(扁桃炎など)
- 薬剤(ステロイドの急な中止、抗菌薬など)
- 妊娠(特に妊娠性膿疱性乾癬)
- 精神的ストレスや過労
重症度とリスク
- 全身性炎症により脱水、肝障害、腎障害を起こすことがある
- 重症例は生命に関わるため入院加療が必要
<膿疱性乾癬(汎発型)>の人はどれくらい?
<膿疱性乾癬(汎発型)>は非常にまれな病気で、全乾癬患者の中でもごく一部しか発症しません。
患者数・頻度の目安
- 国内(日本)
厚生労働省の難病情報センターによると、膿疱性乾癬(全型合計)の患者数はおよそ 500~1,000人程度 と推定されています。
このうち汎発型はその大部分を占めますが、それでも人口10万人あたり1人未満と考えられています。 - 海外データ
欧米でも年間発症率は100万人に1~2人程度とされ、希少疾患に分類されます。
ポイント
- 男女差はあまりないが、日本では中高年女性にやや多い傾向があると報告されています。
- 再発を繰り返すため、統計的な「有病率」は発症数よりやや高めに見積もられることがあります。
- 妊娠期に特有の「妊娠性膿疱性乾癬」はさらにまれで、数十万妊娠に1例程度です。
<膿疱性乾癬(汎発型)>の原因は?
<膿疱性乾癬(汎発型)>の原因は、免疫異常と遺伝的素因が複雑に関与して発症すると考えられています。
1. 免疫の異常
- 自己免疫的な炎症反応が皮膚で過剰に起こり、好中球が皮膚表面に集まって無菌性膿疱を形成します。
- 炎症性サイトカイン(IL-1β、IL-36、TNF-α、IL-17、IL-23など)の過剰産生が中心的役割を果たします。
2. 遺伝的要因
- 日本や中国で、IL36RN遺伝子変異(IL-36受容体拮抗タンパク質の異常)との関連が報告されています。
- この変異があると炎症が制御できず、急性の膿疱発症を引き起こしやすい。
- 他にもCARD14やAP1S3などの変異も関与する例があります。
3. 誘因(引き金)
- 薬剤
- ステロイドの急な中止(リバウンド)
- 抗菌薬、抗真菌薬、一部の降圧薬やNSAIDs
- 感染症(扁桃炎、上気道炎など)
- 妊娠(妊娠性膿疱性乾癬)
- ストレス・過労
- 日焼け・皮膚外傷(ケブネル現象)
4. 他の乾癬との違い
- 尋常性乾癬では慢性的に皮疹が広がりますが、汎発型膿疱性乾癬は急性かつ全身性に発症し、全身症状(発熱、倦怠感、関節痛など)を伴うことが多いです。
<膿疱性乾癬(汎発型)>は遺伝する?
<膿疱性乾癬(汎発型)>は、
「必ず遺伝する病気」ではありませんが、遺伝的素因が関与することがある病気です。
1. 遺伝との関係
- 一部の患者さんでは、IL36RN遺伝子変異などの単一遺伝子異常が原因になることがあります。
- この場合は「自己炎症性疾患(autoinflammatory disease)」の一種として遺伝性といえます。
- 常染色体劣性遺伝のことが多く、両親からそれぞれ変異を受け継いだときに発症します。
- しかし、ほとんどのケースでは**複数の遺伝的背景+環境要因(感染、薬、ストレスなど)**が組み合わさって発症します。
2. 家族歴の有無
- 家族内に同じ病気が複数出ることはありますが、全体ではまれです。
- 家族に乾癬(特に尋常性乾癬)があると発症リスクがやや上がるという報告があります。
3. 遺伝カウンセリングの必要性
- IL36RN変異が疑われる場合、遺伝子検査で確認できます。
- 遺伝性の場合でも発症年齢や重症度は個人差が大きく、必ずしも同じ経過をたどるわけではありません。
<膿疱性乾癬(汎発型)>の経過は?
<膿疱性乾癬(汎発型)>の経過は、急性発症型と慢性再発型に分けられます。どちらの場合も皮膚症状だけでなく全身への影響が強く出やすいのが特徴です。
1. 急性発症型(急性汎発型膿疱性乾癬)
- 突然の高熱(38〜40℃)、全身の発赤とびまん性膿疱が数時間〜数日で出現。
- 膿疱は無菌性(細菌感染によるものではない)。
- 強い倦怠感、関節痛、悪寒などの全身症状を伴う。
- 数日〜数週間で膿疱が乾いて皮がむけ(落屑)、症状が軽快することもあるが、再発することも多い。
- 発症時には肝障害・腎障害・低カルシウム血症など全身合併症が出ることがあり、重症例では命に関わる。
2. 慢性再発型
- 比較的軽い発疹や膿疱が周期的に再燃と寛解を繰り返す。
- 全身症状は軽いこともあるが、皮疹が長期にわたり持続することが多い。
- 再燃のきっかけは感染症、薬剤、ストレス、妊娠、季節の変化など。
3. 特殊型
- 妊娠性膿疱性乾癬:妊娠中に発症し、分娩後に改善するが、胎児や母体に危険がある。
- 小児発症型:遺伝子変異(IL36RN)による例が多く、若年での再発が目立つ。
4. 長期予後
- 適切な治療で症状は抑えられるが、慢性化・再発しやすい。
- 重症発作時には入院管理が必要。
- 合併症(肝障害、腎障害、心血管疾患)や薬の副作用に注意が必要。
<膿疱性乾癬(汎発型)>の治療法は?
<膿疱性乾癬(汎発型)>の治療は、
「急性期の全身状態の安定化」+「再発予防」 の2本柱で行われます。
症状の重さ、発症型(急性/慢性)、原因(遺伝子変異の有無)によって選択肢が変わります。
1. 急性期治療(発作時)
目的:全身炎症の鎮静化、合併症の予防
- 入院管理:高熱や全身発赤、膿疱による体液喪失や電解質異常を防ぐ。
- 安静・保温・水分補給:低カルシウム血症や脱水を防ぐ。
- 全身性薬物療法
- シクロスポリン:免疫抑制作用で炎症を早期に抑える。
- ステロイド全身投与:短期間で急性炎症をコントロール(長期使用は再発や副作用リスクあり)。
- メトトレキサート:免疫抑制+抗炎症作用。
- 感染が疑われる場合:抗菌薬(膿疱は基本無菌だが二次感染防止目的)。
- 電解質・臓器障害対策:低カルシウム血症や肝腎障害の補正。
2. 慢性期・再発予防
目的:炎症の持続や再燃を防ぎ、生活の質(QOL)を保つ
- レチノイド(エトレチナートなど):角化異常と炎症を改善。
- ビタミンD3外用+ステロイド外用:皮疹の維持管理。
- **免疫抑制薬(シクロスポリン、メトトレキサートなど)**の少量長期投与。
- 誘因除去:感染症治療、薬剤中止(特にステロイドの急な中止は発作誘発)、ストレス軽減。
3. 生物学的製剤(2020年代以降の進展)
- IL-17阻害薬(セクキヌマブ、イキセキズマブ)
- IL-23阻害薬(グセルクマブ、リサンキズマブ)
- TNF-α阻害薬(インフリキシマブなど)
- IL-36受容体拮抗薬(スペシフィックな治療、特にIL36RN変異例で有望)
- 2023〜2024年に海外で承認された新薬あり、日本でも臨床試験中。
4. 特殊型への対応
- 妊娠性膿疱性乾癬:母児安全のため、ステロイドやシクロスポリンを短期使用、早期分娩も検討。
- 遺伝子変異型(DITRAなど):IL-1/IL-36経路を標的にした治療が研究中。
<膿疱性乾癬(汎発型)>の日常生活の注意点
<膿疱性乾癬(汎発型)>では、急な全身炎症や再発を防ぐために、
皮膚・全身・生活習慣の3方向から注意が必要です。
1. 皮膚ケア
- 皮膚の乾燥を防ぐ:低刺激の保湿剤を1日数回使用し、角層バリアを保護。
- 掻き壊しや摩擦を避ける:新しい膿疱や皮疹の誘因になる。
- 入浴はぬるめのお湯で短時間:熱い湯・長風呂は皮膚の乾燥とかゆみを悪化。
- 石けんは低刺激・無香料を使用。
2. 体調・環境管理
- 感染症の予防:風邪やインフルエンザは発作の引き金になるため、手洗い・うがい・マスク着用。
- 体温変化や疲労の蓄積を避ける:発熱や体力低下も発症リスク。
- 脱水予防:特に発疹・発熱時は水分・電解質補給をこまめに。
- 定期的な血液検査:肝機能・腎機能・電解質異常の早期発見。
3. 薬・治療の管理
- 医師の指示なくステロイド内服を急に中止しない:リバウンド発作の危険。
- 服薬・注射スケジュールを守る:生物学的製剤・免疫抑制薬は効果持続のため定期投与が必要。
- 新しい薬を使う前に医師に相談:一部薬剤(リチウム、β遮断薬など)が悪化要因。
4. 食事・生活習慣
- バランスの良い食事:高タンパク・適度なビタミン・ミネラル摂取で皮膚修復を促進。
- アルコールは控えめに:肝臓への負担や炎症悪化を防ぐ。
- 禁煙:血流改善と皮膚炎症リスク低減。
- 十分な睡眠とストレス管理:心理的ストレスも再発の引き金。
5. メンタルサポート
- 外見変化によるストレスや社会的制約があるため、家族や支援団体、心理士とつながることが有用。
- オンライン患者会やSNSで同病者と情報交換する方法もある。