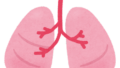目次
<下垂体前葉機能低下症>はどんな病気?
🔹 定義
- 下垂体前葉から分泌される複数のホルモンが不足する病気です。
- 下垂体前葉は脳の中央にある小さな器官で、全身のホルモン分泌をコントロールする「司令塔」のような役割を持っています。
- この部分の障害によって、副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン、性ホルモン、成長ホルモンなどが不足し、全身にさまざまな症状が現れます。
🔹 主な原因
- 下垂体腺腫(良性腫瘍)による圧迫
- 脳外科手術や放射線治療後
- 脳出血や外傷
- 自己免疫性・炎症性疾患(下垂体炎など)
- 先天性の下垂体形成異常
- シーハン症候群(分娩時の大量出血による下垂体壊死)
🔹 不足するホルモンと症状
下垂体前葉は以下のホルモンを分泌します。
- **ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)**不足 → 低血圧、低血糖、疲労感
- **TSH(甲状腺刺激ホルモン)**不足 → 倦怠感、体重増加、冷え、むくみ
- **LH/FSH(性腺刺激ホルモン)**不足 → 月経異常、不妊、性欲低下
- **GH(成長ホルモン)**不足 → 小児では成長障害、成人では筋力低下・脂質代謝異常
- **PRL(プロラクチン)**不足 → 乳汁分泌不全(出産後)
🔹 病気の特徴
- 不足するホルモンの種類・程度によって症状はさまざま。
- 徐々に進行することが多く、初期には「疲れやすい」「元気がない」など非特異的な症状のみで見逃されやすい。
- 適切にホルモン補充療法を行えば、生活の質を大きく改善できる。
✅ まとめ
<下垂体前葉機能低下症>とは、下垂体前葉が障害されることで複数のホルモンが不足し、全身に影響が出る病気です。
原因は腫瘍や外傷、分娩時の出血などさまざまで、不足するホルモンによって症状は異なります。
<下垂体前葉機能低下症>の人はどれくらい?
🔹 世界的な頻度
- 下垂体前葉機能低下症(Hypopituitarism)は、まれな疾患に分類されます。
- 世界での有病率は報告によって差がありますが、人口10万人あたり30〜45人程度とされています。
- 年間発症率は 人口10万人あたり約2〜4人 と推定されています。
🔹 日本での頻度
- 日本においても「希少疾患」の一つです。
- 厚生労働省の特定疾患(指定難病)には登録されており、患者数は数千人規模と推定されています。
- シーハン症候群(分娩時の大量出血による発症)は減少傾向にありますが、下垂体腺腫や手術後の発症が比較的多く報告されています。
🔹 年齢・性別の傾向
- 発症年齢は幅広いですが、30〜60歳代に多い。
- 男女差は大きくないが、原因が産後合併症(シーハン症候群)の場合は女性特有。
✅ まとめ
- <下垂体前葉機能低下症>は、人口10万人あたり30〜45人程度のまれな病気。
- 日本でも患者数は数千人規模。
- 主因は下垂体腺腫や治療後、まれに分娩時の大量出血など。
<下垂体前葉機能低下症>の原因は?
🔹 大きな分類
下垂体前葉機能低下症の原因は、大きく 器質的な障害(下垂体や視床下部の損傷) と 機能的・全身的な要因 に分けられます。
🔹 主な原因
1️⃣ 器質的原因
- 下垂体腺腫(良性腫瘍)
- 最も多い原因。腫瘍の圧迫や手術・放射線治療によって機能が低下。
- 頭部外傷・脳出血
- 外傷やくも膜下出血、下垂体卒中(下垂体腺腫内の出血や梗塞)で発症することがある。
- 手術や放射線治療の後遺症
- 脳腫瘍治療や頭蓋咽頭腫治療などに伴うもの。
- 炎症・感染
- 下垂体炎(自己免疫性・肉芽腫性など)、結核、真菌感染。
- 先天性異常
- 下垂体形成不全、遺伝子変異によるホルモン分泌異常。
2️⃣ 全身的・機能的原因
- シーハン症候群
- 出産時の大量出血による下垂体壊死。歴史的には多かったが、近年は減少。
- 慢性疾患に伴う二次性変化
- サルコイドーシス、ヘモクロマトーシス(鉄沈着症)など。
- 視床下部障害
- 視床下部腫瘍(頭蓋咽頭腫など)、外傷、炎症により下垂体への刺激ホルモン分泌が低下。
🔹 特徴
- 単一のホルモンのみが不足する場合もあるが、複数のホルモンが同時に不足する「汎下垂体機能低下症」として現れることも多い。
- 原因の中では 下垂体腺腫およびその治療後 が最も頻度が高い。
✅ まとめ
<下垂体前葉機能低下症>の原因は、
- 下垂体腺腫・治療後・外傷・出血・炎症などによる器質的障害が主因。
- まれに 出産時の大量出血(シーハン症候群) や 先天性異常 もある。
<下垂体前葉機能低下症>は遺伝する?
🔹 基本的な考え方
- 下垂体前葉機能低下症の 多くは遺伝性ではなく、後天的に発症 します。
- 例:下垂体腺腫や手術・放射線治療の後遺症、外傷、シーハン症候群など。
- そのため、一般的に「家族に遺伝する病気」ではありません。
🔹 遺伝的要因が関与するケース
まれに、先天性/遺伝性の下垂体前葉機能低下症 が存在します。
- 遺伝子変異による先天性下垂体形成異常
- HESX1、PROP1、POU1F1、LHX3、LHX4、SOX2、SOX3 などの遺伝子異常が報告されています。
- これらは下垂体の発生やホルモン産生に関わる転写因子の異常。
- 常染色体劣性遺伝や常染色体優性遺伝の形式をとる場合がある。
- 特に PROP1 変異は「小児期〜思春期に徐々に複数の下垂体ホルモンが欠損するタイプ」として知られている。
🔹 まとめ
- <下垂体前葉機能低下症>は ほとんどが後天性で遺伝しない。
- しかし一部で 先天性・遺伝性のタイプ があり、特定の転写因子遺伝子の異常によって家族性にみられることがある。
<下垂体前葉機能低下症>の経過は?
🔹 経過の特徴
- 下垂体前葉機能低下症は、どのホルモンが欠乏するか・どの程度か によって経過が異なります。
- 多くはゆっくり進行し、最初は症状が目立たないこともあります。
- 治療(ホルモン補充)を適切に行えば、生活の質(QOL)は大きく改善できます。
🔹 病型ごとの経過
1️⃣ 急性発症型
- 下垂体卒中(腺腫内の出血・梗塞)やシーハン症候群では、数時間〜数日で急激にホルモン欠乏が進み、ショック・低血糖・低血圧など重篤な症状を呈する。
- 治療が遅れると命に関わる。
2️⃣ 慢性進行型
- 下垂体腺腫や術後・放射線後遺症では、数年単位で徐々にホルモン分泌が低下。
- 最初は一部のホルモン(例:性腺刺激ホルモン)から欠乏し、次第に多ホルモン欠損へ進行。
- 倦怠感・性欲低下・無月経など軽微な症状から始まり、やがて副腎不全や甲状腺機能低下など全身症状に至る。
3️⃣ 先天性・遺伝性
- 出生時からホルモン分泌が不足。
- 小児では成長障害や思春期の遅れが主な経過。
- 成人に至ってから診断される例もある。
🔹 治療を行った場合の経過
- 不足しているホルモンを生涯にわたって補充する必要がある。
- 適切に治療すれば、ほぼ健康に近い生活が可能。
- ただし、副腎不全(コルチゾール不足)や甲状腺機能低下は急変時に命に関わるため、補充薬の自己調整・緊急対応(ステロイド注射など)の指導が必須。
🔹 治療を行わなかった場合
- 徐々に体力低下、低血糖、低血圧、無月経、不妊、意識障害などを経て、重篤な副腎クリーゼ(急性副腎不全)を起こす危険が高い。
✅ まとめ
- <下垂体前葉機能低下症>の経過は、急性発症型と慢性進行型がある。
- 適切にホルモン補充を行えば予後は良好で、ほぼ通常の生活が可能。
- 治療を怠ると、副腎不全や甲状腺機能低下から生命に関わる急変を起こすことがある。
<下垂体前葉機能低下症>の治療法は?
🔹 基本方針
- 下垂体前葉機能低下症は 失われたホルモンを補充すること が治療の中心です。
- 多くの場合、原因(腫瘍など)の治療と、生涯にわたるホルモン補充療法が必要となります。
- 複数のホルモンが不足している場合は、補充の順序も重要です(特に副腎ホルモンを先に補充する)。
🔹 原因への治療
- 下垂体腺腫 → 手術(経蝶形骨洞手術)、放射線治療
- 炎症や感染 → ステロイド、抗菌薬 など
- 出血や外傷 → 急性期管理
- ただし、多くの場合は原因を治してもホルモン分泌は完全には回復せず、補充療法が必要になります。
🔹 ホルモン補充療法(HRT)
不足するホルモンごとに補充を行います。
1️⃣ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)不足
- 直接ACTHは使わず、ヒドロコルチゾン(コートリル®)などの副腎皮質ホルモンを補充。
- ストレス時(発熱、手術、外傷)には増量が必要(「シックデイ・ルール」)。
2️⃣ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)不足
- **レボチロキシン(チラーヂンS®)**で甲状腺ホルモン補充。
⚠ ただし、必ず副腎皮質ホルモンを先に補充しないと副腎クリーゼを誘発する危険がある。
3️⃣ 性腺刺激ホルモン(LH・FSH)不足
- 男性:テストステロン補充(注射・外用剤)
- 女性:エストロゲン+プロゲステロン補充
- 不妊希望の場合は ゴナドトロピン注射(hCG、FSH製剤)やGnRHパルス療法で排卵・精子形成を誘導。
4️⃣ 成長ホルモン(GH)不足
- 小児:GH注射で成長を促す。
- 成人:希望・適応があればGH補充で体組成・QOL改善。
5️⃣ プロラクチン(PRL)不足
- 特に治療は不要(乳汁分泌不全が主症状のため)。
🔹 補助療法・管理
- 在宅自己注射や内服の継続が基本。
- 定期的な血液検査でホルモン量・代謝状態を確認。
- 患者は「副腎不全カード」や「緊急時用ステロイド注射」を携帯することが推奨される。
✅ まとめ
- 治療の中心は ホルモン補充療法。
- 特に重要なのは 副腎皮質ホルモンを最優先で補充すること。
- 性ホルモンや成長ホルモンも必要に応じて補充し、QOLと生命予後を改善できる。
- 生涯にわたり治療が必要だが、適切な管理でほぼ健常に近い生活が可能。
<下垂体前葉機能低下症>の日常生活の注意点
🔹 1. 薬の自己管理
- ホルモン補充療法は一生涯続くため、内服や注射を自己判断で中断しない。
- 特に副腎皮質ホルモン(ヒドロコルチゾンなど)は必須。忘れると生命に関わる。
- 旅行や外出時には薬を切らさないように余裕を持って準備。
🔹 2. ストレス・病気時の対応
- 発熱・手術・外傷・強いストレス時には ステロイド補充量を増やす(シックデイ・ルール)。
- 主治医の指導に従い、自己調整の仕方を学んでおく。
- 急変時に備えて **緊急用の注射(ヒドロコルチゾン筋注)**を準備し、家族も使い方を知っておく。
🔹 3. 感染症・体調管理
- 感染症は副腎不全を誘発する危険因子。
- 日常から手洗い・うがい、ワクチン接種(インフルエンザ・肺炎球菌など)で予防。
- 体調不良が長引く場合は早めに医療機関を受診。
🔹 4. 栄養・運動
- 栄養バランスを意識(カルシウム・ビタミンD → 骨粗鬆症予防)。
- 性ホルモン欠乏があると骨密度低下リスクがあるため、定期的な骨検査も重要。
- 軽い運動(ウォーキング・ストレッチ)は体力維持に有効。
🔹 5. 妊娠・出産を希望する場合
- 女性は性腺ホルモン補充や排卵誘発が必要になることがある。
- 妊娠中はホルモン補充量を調整することもあるので、主治医と計画的に管理。
🔹 6. セルフケアと周囲への周知
- 「副腎不全カード」や「医療アラート(IDカード・ブレスレット)」を常に携帯し、救急時に医療者へ伝えられるようにする。
- 家族・学校・職場に「ステロイドが必須であること」「体調不良時は補充が必要なこと」を知らせておく。
✅ まとめ
<下垂体前葉機能低下症>の日常生活で大切なのは:
- 薬を切らさず正しく服用すること
- 病気やストレス時にステロイドを増量する「シックデイ・ルール」を守ること
- 感染症や骨粗鬆症への予防対策
- 緊急時対応(副腎不全カード・注射薬の準備)
- 周囲への情報共有
<下垂体前葉機能低下症>の最新情報
“Empty sella”(頭蓋内の sella 膜に間隙がある状態)を持つ患者の前葉機能を解析。(2025)
下垂体腺腫に対し放射線治療を行った局所制御率(tumor local control)が良好ただし、下垂体前葉機能低下症(2025)