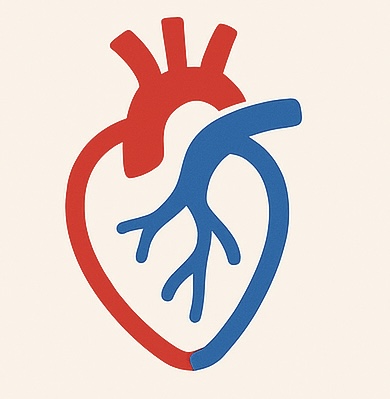目次
<拘束型心筋症>はどんな病気?
◆ どんな病気か
拘束型心筋症は、心筋の「硬さ」が増して心臓が拡張しにくくなる病気です。
その結果、心臓に血液がうまく入らない(拡張障害)ことが主な問題となります。
- 心臓の収縮力(ポンプとして血液を送り出す力)は比較的保たれています。
- しかし心筋が硬くなるため、心室が十分に広がらず血液を取り込めない → 心房や静脈に血液が滞り、肺うっ血や体のむくみを起こします。
- 進行すると心不全の症状(息切れ・倦怠感・浮腫)が強くなります。
◆ 原因
拘束型心筋症はまれな心筋症で、原因は様々です。
- 遺伝性
- サルコメア遺伝子の変異など、肥大型心筋症に関連するものの一部が拘束型の形を取ることがあります。
- 後天性・二次性
- アミロイドーシス(異常タンパク沈着)
- サルコイドーシス(炎症性肉芽腫)
- 放射線治療や化学療法の後遺症
- ヘモクロマトーシス(鉄沈着症)
- 特発性(原因不明)
◆ 主な症状
- 労作時の息切れ
- 動悸
- 下肢のむくみ
- 起座呼吸(横になると息苦しい)
- 進行すると不整脈や血栓塞栓症のリスク
◆ 他の心筋症との違い
- 肥大型心筋症:心筋が分厚くなる
- 拡張型心筋症:心筋が薄く弱くなり、収縮力が低下する
- 拘束型心筋症:心筋は厚くも薄くもないが「硬く」なり、拡張できなくなる
👉 まとめると、拘束型心筋症は「心臓が硬くなって血液を受け入れられない」ことで心不全を引き起こすまれな病気です。
<拘束型心筋症>の人はどれくらい?
有病率・頻度
- 非常に稀な心筋症であり、心筋症全体の 約3〜5%程度 を占めるにすぎません。
- 欧米や日本の疫学研究でも、肥大型心筋症(HCM)や拡張型心筋症(DCM)に比べてはるかに少なく、人口10万人あたり数人程度と推定されています。
- 成人だけでなく小児にも発症しますが、小児例はさらにまれです。
地域差
- 欧米・日本:特発性RCMは極めて稀。アミロイドーシスなどの続発性RCMが比較的多い。
- アフリカ・アジアの一部:寄生虫感染や栄養状態に関連した「心内膜心筋線維症(Endomyocardial fibrosis, EMF)」によるRCMが比較的多い。
実際の患者像
- 日本では正確な患者数の全国統計は存在しませんが、専門施設の報告からも「心筋症患者の中で最も少数派」とされています。
- 多くは**基礎疾患(例:アミロイドーシス、サルコイドーシス、ヘモクロマトーシスなど)**に伴って発症します。
👉まとめると、拘束型心筋症は心筋症の中でも最も稀なタイプで、人口あたり数人程度しかいないと考えられています。
<拘束型心筋症>の原因は?
拘束型心筋症(Restrictive cardiomyopathy, RCM)の原因は大きく分けて 一次性(特発性) と 二次性(基礎疾患に伴うもの) に分類されます。
1. 一次性(特発性)拘束型心筋症
- 原因不明のもの。遺伝的素因が関わっていると考えられるケースもあります。
- 心筋そのものが硬くなり、心室の拡張が制限されることで発症します。
2. 二次性拘束型心筋症
他の疾患によって心筋や心内膜が硬くなることが原因です。代表的なものには以下があります。
● 浸潤性疾患
- アミロイドーシス(心臓アミロイドーシス):アミロイド蛋白が心筋に沈着して硬くなる。
- サルコイドーシス:心筋に肉芽腫が形成される。
● 貯蔵病(代謝異常症)
- ムコ多糖症、糖原病、ヘモクロマトーシス(鉄沈着症)など。
● 心内膜・心筋の線維化
- 放射線治療の晩期障害による線維化。
- 特発性心内膜線維弾性症。
- トロピカル・エンドミオカーディアルファイブローシス(熱帯地方で多い)。
3. 原因不明のことも多い
実際には「特発性」とされる場合も少なくありません。診断では、拡張型心筋症や肥大型心筋症、心タンポナーデなどとの鑑別が重要です。
👉 まとめると、拘束型心筋症は 心筋が硬くなって心臓が拡張できなくなる病気 で、
その原因は「アミロイドーシスやサルコイドーシスなどの浸潤性疾患」「代謝異常症」「放射線治療後の線維化」などが代表的です。
「日本人に多い原因」と「遺伝との関わり」
日本人に多い拘束型心筋症の原因
日本では熱帯地方で多い「熱帯性心内膜線維症」はほとんど見られません。代わりに、以下が多いです。
1. 心アミロイドーシス
- 日本で最も代表的な原因。
- 特に トランスサイレチン型(ATTR型) が増えていて、遺伝子変異による遺伝性型と、加齢に伴う野生型(以前は老人性心アミロイドーシスと呼ばれた)があります。
- 高齢男性に多く、「原因不明の心不全」「不整脈」で発見されることが多いです。
2. サルコイドーシス
- 日本人は比較的頻度が高い。
- 心臓サルコイドーシスは不整脈や伝導障害を起こしやすく、拘束型心筋症に似た経過をたどることがあります。
3. 放射線治療後の心筋障害
- 乳がんやリンパ腫などで胸部に放射線治療を受けた人に見られます。
- 年数を経てから心内膜・心筋が硬くなり拘束型の病態をとることがあります。
遺伝との関わり
- アミロイドーシス(ATTR型)
- 遺伝性:トランスサイレチン遺伝子の変異による。日本では秋田・長野などに家族集積例が知られています。
- 非遺伝性:加齢に伴い誰にでも起こりうる「野生型」。
- その他の代謝性疾患
- ヘモクロマトーシス(鉄沈着症)、糖原病、ムコ多糖症なども遺伝的背景がありますが、日本ではまれです。
- 肥大型心筋症から拘束型への移行
- 遺伝子変異により起こる肥大型心筋症が進行すると、拘束型のような臨床像を示す場合があります。
✅ まとめると
- 日本では「アミロイドーシス」と「サルコイドーシス」が主要因。
- 遺伝的要因としては「トランスサイレチン遺伝子変異による家族性アミロイドーシス」が代表的です。
- ただし「加齢に伴う非遺伝性アミロイドーシス」も非常に多く、高齢者の心不全の隠れた原因になっています。
<拘束型心筋症>は遺伝する?
拘束型心筋症(RCM)は すべてが遺伝するわけではなく、原因によって「遺伝性のもの」と「非遺伝性のもの」があります。
🔹 遺伝するケース
1. 遺伝性アミロイドーシス
- トランスサイレチン(TTR)遺伝子変異による家族性アミロイドーシスは、常染色体優性遺伝。
- 家族内で世代を超えて発症することがあり、日本でも秋田・長野などの地域に患者集積が知られています。
2. 家族性拘束型心筋症
- 稀ですが、心筋収縮タンパク質(トロポニンI、トロポニンT、βミオシン重鎖など)の サルコメア遺伝子変異 によって発症することがあります。
- 同じサルコメア変異で「肥大型心筋症(HCM)」や「拡張型心筋症(DCM)」になることもあり、遺伝子型により表現型が分かれる場合があります。
3. 代謝性・貯蔵病によるもの
- 糖原病(Pompe病など)、ムコ多糖症、ファブリー病、ヘモクロマトーシス(鉄沈着症) などは遺伝性疾患として起こり得ます。
🔹 遺伝しないケース
- 野生型トランスサイレチン心アミロイドーシス(加齢性) → 高齢者に多いが遺伝はしない。
- サルコイドーシス → 遺伝要因は弱く、自己免疫・炎症反応が関与。
- 放射線治療後の心筋障害 → 後天的。
- 特発性(原因不明)RCM → 遺伝的要因が見つからないこともある。
✅ まとめ
- 遺伝性:TTR変異アミロイドーシス、サルコメア遺伝子変異、代謝異常症など。
- 非遺伝性:加齢による野生型アミロイドーシス、サルコイドーシス、放射線後障害、原因不明例など。
つまり、拘束型心筋症の中でも「遺伝するタイプ」と「遺伝しないタイプ」があり、臨床では遺伝性アミロイドーシスやサルコメア遺伝子異常が特に注目されています。
拘束型心筋症における遺伝するタイプ/しないタイプの見分け方
1. 家族歴の聴取
- 遺伝性が疑われる最初の手がかりは家族歴です。
- 両親や兄弟姉妹、子どもに同様の心不全・不整脈・心筋症があるか?
- 特に「若年で心不全」「原因不明の突然死」が家系に多い場合は遺伝性の可能性大。
2. 遺伝子検査
- サルコメア遺伝子パネル検査
- トロポニンI(TNNI3)、トロポニンT(TNNT2)、β-ミオシン重鎖(MYH7)など。
- 家族性RCMや肥大型心筋症・拡張型心筋症とのオーバーラップを確認可能。
- トランスサイレチン(TTR)遺伝子検査
- 家族性アミロイドーシスが疑われる場合に必須。
- 特定の変異(例:Val30Met変異)は日本の一部地域で多い。
- 代謝性疾患関連遺伝子
- ファブリー病(GLA遺伝子)、糖原病(GAA遺伝子)など。
3. 心筋生検(エンドミオカーディアルバイオプシー)
- 顕微鏡的に心筋組織を確認する方法。
- アミロイド沈着(特殊染色:コンゴーレッド染色でアップルグリーン偏光)やサルコイドーシス(非乾酪性肉芽腫)を確認できる。
- 遺伝子検査と組み合わせることで「遺伝性アミロイドーシス」か「加齢性アミロイドーシス」かを見分けやすくなる。
4. 画像検査
- 心エコー
- 壁厚が増しているのに心室が拡大しない → 拘束型を疑う。
- アミロイドーシスでは“スパークリング”と呼ばれる顆粒状反射が特徴的。
- 心臓MRI(Late Gadolinium Enhancement, LGE)
- アミロイドーシス:びまん性遅延造影。
- サルコイドーシス:斑状の造影。
- 遺伝性疾患かどうかの決め手にはならないが、鑑別に有用。
- 核医学(^99mTc-PYPシンチ)
- トランスサイレチン型アミロイドーシスを強く示唆する。
- ALアミロイドーシス(免疫グロブリン由来)との鑑別に使われる。
5. 血液・尿検査
- アミロイドーシスの鑑別
- AL型アミロイドーシス(免疫グロブリン由来)を除外するために血清・尿の免疫電気泳動や遊離軽鎖測定。
- 酵素活性測定
- ファブリー病など代謝性疾患を疑うときに有効。
✅ まとめ
- 遺伝性かどうかを見分けるには「家族歴+遺伝子検査」が中心。
- 心筋生検・画像検査・核医学検査を組み合わせることで、アミロイドーシスなど原因の特定が可能。
- 特に日本では「TTR遺伝子検査」と「PYPシンチ」がアミロイドーシス診断で重要。
<拘束型心筋症>の経過は?
拘束型心筋症(Restrictive cardiomyopathy, RCM)の経過は、原因や治療介入の有無によって差がありますが、共通して 「心臓が硬くなり拡張できない → 心不全が進行する」 という流れをたどります。以下に整理しますね。
🔹 拘束型心筋症の経過
1. 初期(無症状〜軽度)
- 心筋の拡張が少し制限される段階。
- 自覚症状は乏しく、健診の心電図異常や心エコーで偶然発見されることもある。
- 運動時に軽い息切れや疲れやすさを感じる程度。
2. 進行期(心不全の顕在化)
- 心室が十分に広がらず、拡張障害型心不全(HFpEF) の形で症状が出てくる。
- 労作時の息切れ、動悸、浮腫(むくみ)、体重増加、夜間呼吸困難など。
- 心房は血液を溜めるために拡大し、心房細動や心房粗動などの 不整脈 が出やすい。
- 脳梗塞などの塞栓症を起こすリスクも増える。
3. 末期(高度進行)
- 心臓の拡張機能がさらに落ち、全身の血流維持が難しくなる。
- 右心不全症状(頸静脈怒張、肝腫大、腹水、下肢浮腫)が目立つ。
- 利尿薬や心不全治療薬でコントロールが困難になることが多い。
- 不整脈による突然死のリスクもある。
4. 特殊な経過
- アミロイドーシス由来:進行が比較的速い(数年単位で悪化)。
- サルコイドーシス由来:炎症のコントロールができれば進行が抑えられる場合あり。
- 家族性RCMや代謝性疾患:小児〜若年から発症し、進行が速いことがある。
🔹 予後(一般的な見通し)
- 全体的に 拡張型や肥大型心筋症より予後が悪い とされる。
- 特にアミロイドーシスでは、診断から平均生存が数年とされてきたが、
近年は トランスサイレチン安定化薬(タファミジスなど) により延命が期待できるようになった。 - 心臓移植が適応になるケースもあるが、全員に適用できるわけではない。
✅ まとめ
拘束型心筋症は
- 初期は無症状〜軽い息切れ
- 心不全症状が顕在化(HFpEF、不整脈、塞栓症)
- 末期には全身のうっ血・多臓器障害・突然死リスク
という経過をたどる病気です。
<拘束型心筋症>の治療法は?
拘束型心筋症(Restrictive cardiomyopathy, RCM)は「心臓が硬くなり拡張できない」ことが本質なので、根本的に治す治療法は少なく、原因に応じた治療と心不全の対症療法が中心になります。以下に整理します。
🔹 拘束型心筋症の治療法
1. 原因疾患に対する治療
RCMは二次性が多いため、原因治療が可能なら優先されます。
- アミロイドーシス
- トランスサイレチン型(ATTR型)
→ タファミジス(Tafamidis):TTRタンパク質を安定化し、進行を抑える。
→ 新薬(RNA干渉薬パチシラン、アンチセンス薬イノテルセン)も使用可能。 - 免疫グロブリン由来(AL型)
→ 化学療法(ボルテゾミブ、メルファランなど)や造血幹細胞移植。
- トランスサイレチン型(ATTR型)
- サルコイドーシス
→ ステロイド(プレドニゾロン)や免疫抑制薬で炎症を抑える。 - 代謝・貯蔵病(ファブリー病など)
→ 酵素補充療法や分子標的治療。 - 放射線後障害・特発性
→ 根治的治療は難しい。心不全の支持療法が中心。
2. 心不全に対する支持療法
- 利尿薬(フロセミドなど):浮腫・胸水・腹水を軽減。
- 塩分制限・水分管理:体液貯留を防ぐ。
- β遮断薬・ACE阻害薬・ARB:症状軽減に使われることもあるが、左室駆出率が保たれているため効果は限定的。
- 抗不整脈薬やペースメーカー/ICD:心房細動や伝導障害・致死性不整脈に対応。
- 抗凝固療法:心房細動や心房拡大に伴う血栓塞栓症予防。
3. 末期治療
- 心臓移植
→ 若年者・全身状態が保たれている場合に適応。 - 補助人工心臓(VAD)
→ 一部でブリッジ治療として使われるが、RCMでは効果が限定的。
🔹 治療の限界と新しい展開
- 従来は「対症療法しかない → 予後不良」だったが、
近年は タファミジスやRNA干渉薬などの分子標的治療 により、アミロイドーシス由来RCMの予後改善が期待できるようになっています。 - ただし、遺伝性か加齢性か、AL型かATTR型か で治療選択がまったく変わるため、診断の精密化が非常に大切です。
✅ まとめ
- 原因治療:アミロイドーシス → タファミジスや化学療法、サルコイドーシス → ステロイド、代謝病 → 酵素補充など。
- 支持療法:利尿薬、抗不整脈薬、抗凝固薬、ペースメーカーなど。
- 進行例:心臓移植を検討。
- 最近はアミロイドーシス治療薬の進歩により「治らない病気」から「進行を遅らせられる病気」へと変わりつつあります。
<拘束型心筋症>の日常生活の注意点
🏡 拘束型心筋症の日常生活の注意点
1. 食生活
- 塩分制限:1日6g未満を目安に(心不全悪化を防ぐ)。
- 水分管理:むくみ・胸水・腹水が出やすいため、主治医と相談して水分量を調整。
- 体重管理:毎日同じ時間に体重測定し、急な増加(1〜2kg/数日間)は心不全のサイン。
- アルコール:心筋障害を悪化させる可能性があるため控えめに。
- バランスの良い食事:特にタンパク質不足や過度なダイエットは避ける。
2. 運動
- 過度な運動は禁止:無理をすると急に心不全が悪化することがある。
- 適度な運動:散歩や軽いストレッチなど、自覚症状が出ない範囲で。
- 息切れ・動悸が出たら中止。
- 医師の指導があれば、心リハ(心臓リハビリテーション)に参加すると安全。
3. 感染予防
- 風邪やインフルエンザが心不全を悪化させることがある。
- ワクチン接種(インフルエンザ・肺炎球菌)は推奨。
- 手洗い・うがい・マスクで予防。
4. 日常生活の工夫
- 禁煙:喫煙は血管を収縮させ、心臓の負担を増やす。
- ストレスをためない:自律神経の乱れや不整脈を防ぐ。
- 睡眠:しっかり休養をとる(あなたの場合、基礎疾患で7時間以上必要ですね☝️)。
- 旅行や外出:遠出する際は、かかりつけ医に相談。高地や高温多湿の環境は注意。
5. 薬の管理
- 利尿薬・抗凝固薬・アミロイドーシス治療薬など、処方薬を正しく服用。
- 飲み忘れや自己中断は危険。
- サプリや市販薬は主治医に相談(相互作用のリスクあり)。
6. 定期受診と家族対応
- 定期的な心エコー・心電図・採血などで病状をモニター。
- 遺伝性が疑われる場合(例:TTR変異) → 家族の遺伝カウンセリング・検査も検討。
✅ まとめ
- 食生活:減塩・水分制限・体重管理。
- 運動:軽めで無理しない。
- 感染予防:ワクチン・手洗い・うがい。
- 生活習慣:禁煙・休養・ストレス管理。
- 薬管理と定期受診が最重要。