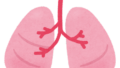目次
<下垂体性PRL分泌亢進症>はどんな病気?
- 🔹 定義
- 🔹 主な原因
- 🔹 症状
- 🔹 検査
- 1️⃣ 全体の中での位置づけ
- 2️⃣ 人口あたりの有病率
- 3️⃣ 日本での推定
- 4️⃣ 他の原因によるPRL高値
- 1️⃣ プロラクチノーマ(PRL産生下垂体腺腫)
- 2️⃣ 下垂体柄圧迫(stalk effect)
- 3️⃣ 薬剤性
- 4️⃣ 全身性疾患・代謝性要因
- 5️⃣ その他
- 🔹 基本的な考え方
- 1️⃣ 多発性内分泌腫瘍症1型(MEN1)
- 2️⃣ AIP遺伝子変異(家族性下垂体腺腫, FIPA)
- 3️⃣ Carney complex, MEN4 など
- ① 初期
- ② 進行期
- ③ 長期経過
- 🔹 基本方針
- 🔹 1. 薬物療法(第一選択)
- 🔹 2. 手術療法
- 🔹 3. 放射線療法
- 🔹 4. 薬剤性・二次性PRL高値の場合
- 🔹 1. 生活全般での注意点
- 🔹 2. 食生活
- 🔹 3. 運動
- 🔹 4. 妊娠・出産を考えている場合(女性)
- 🔹 5. 薬との付き合い方
- ✅ まとめ
🔹 定義
- 下垂体前葉から分泌される プロラクチン(PRL) が過剰に分泌される病気です。
- プロラクチンは本来、乳腺を刺激して乳汁を分泌させるホルモンで、妊娠・授乳期に重要な働きをします。
- しかし、妊娠や授乳と関係なくPRLが高値になると、様々な症状や合併症を起こします。
🔹 主な原因
- プロラクチノーマ(PRL産生下垂体腺腫)
- 下垂体腺腫の中で最も多いタイプ(全下垂体腺腫の約30〜40%)。
- 自律的にPRLを分泌し続ける。
- 下垂体腺腫以外の要因
- 下垂体や視床下部の病変(圧迫でドパミンの抑制が効かなくなる)。
- 薬剤(抗精神病薬、抗うつ薬、制吐薬などドパミン遮断作用を持つ薬)。
- 甲状腺機能低下症(TRH上昇によりPRL分泌が亢進)。
- 慢性腎不全(PRL排泄低下)。
🔹 症状
- 女性
- 無月経・月経不順
- 不妊
- 乳汁分泌(非妊娠・非授乳時)
- 性欲低下
- 男性
- 性欲低下、勃起不全
- 不妊
- 女性化乳房
- 共通
- 腫瘍が大きい場合、頭痛・視野障害など下垂体腫瘍による圧迫症状。
🔹 検査
- 血液検査:PRL高値。
- MRI:下垂体腺腫(マイクロ腺腫:10mm未満、マクロ腺腫:10mm以上)を確認。
<下垂体性PRL分泌亢進症>の人はどれくらい?
1️⃣ 全体の中での位置づけ
- **プロラクチノーマ(PRL産生下垂体腺腫)**が原因の大半を占めます。
- プロラクチノーマは 下垂体腺腫全体の30〜40% を占め、最も多いタイプです。
2️⃣ 人口あたりの有病率
- 一般人口での有病率は 10万人あたり約 prolactinoma 50〜100人 と報告されています。
- 男女比では、女性(特に20〜40代)に多く、男性は女性の1/3〜1/5程度。
3️⃣ 日本での推定
- 日本全体で考えると、少なくとも 数万人規模の患者が存在 すると推測されます。
- ただし無症状で発見されないケースも多く、実際には潜在患者数はさらに多い可能性があります。
4️⃣ 他の原因によるPRL高値
- 薬剤性(抗精神病薬・抗うつ薬など)、慢性腎不全、甲状腺機能低下症などでもPRL高値が起こる。
- この場合は「下垂体性PRL分泌亢進症」ではなく「二次性高プロラクチン血症」と区別されます。
<下垂体性PRL分泌亢進症>の原因は?
🔹 主な原因
1️⃣ プロラクチノーマ(PRL産生下垂体腺腫)
- 最も代表的で、下垂体性PRL分泌亢進症の大多数を占める。
- 下垂体前葉の腺腫が自律的にプロラクチンを過剰分泌する。
- 腺腫の大きさによって
- マイクロ腺腫(10mm未満)
- マクロ腺腫(10mm以上)
に分類される。
- 腫瘍が大きいとホルモン異常に加えて、頭痛・視野障害など圧迫症状が出る。
2️⃣ 下垂体柄圧迫(stalk effect)
- 下垂体やその周囲の腫瘍(非PRL腺腫、頭蓋咽頭腫、髄膜腫など)が下垂体茎を圧迫すると、
- 本来PRL分泌を抑えるドパミンの下垂体への流れが阻害され、
- 二次的にPRLが上昇する。
3️⃣ 薬剤性
- ドパミン遮断薬が最も多い原因。
- 抗精神病薬(リスペリドン、ハロペリドールなど)
- 抗うつ薬の一部(SSRIなど)
- 制吐薬(メトクロプラミドなど)
- これらは下垂体へのドパミン作用をブロックし、PRL分泌が抑制されなくなる。
4️⃣ 全身性疾患・代謝性要因
- 甲状腺機能低下症:TRHが上昇し、その刺激でPRLが過剰分泌される。
- 慢性腎不全:PRLの排泄が低下し、血中濃度が上がる。
- 肝疾患:代謝低下でPRLが蓄積。
5️⃣ その他
- 胸部刺激(胸部外傷・授乳刺激・乳頭刺激)による一過性上昇。
- 原因不明(特発性高プロラクチン血症)。
<下垂体性PRL分泌亢進症>は遺伝する?
🔹 基本的な考え方
<下垂体性PRL分泌亢進症>は大部分が プロラクチノーマ(PRL産生下垂体腺腫) によるもので、
多くは散発性(偶発的に起こる)で遺伝しない と考えられます。
🔹 遺伝に関係する特殊なケース
1️⃣ 多発性内分泌腫瘍症1型(MEN1)
- MEN1遺伝子(menin遺伝子)の変異によって起こる常染色体優性遺伝疾患。
- 副甲状腺腫瘍、膵神経内分泌腫瘍、下垂体腫瘍(プロラクチノーマが多い) を合併する。
- この場合、家族内で複数人にPRL分泌亢進症が出ることがある。
2️⃣ AIP遺伝子変異(家族性下垂体腺腫, FIPA)
- 若年発症の下垂体腺腫に関連する遺伝性素因。
- GH産生腺腫が多いが、プロラクチノーマも含まれる。
- 常染色体優性遺伝。
3️⃣ Carney complex, MEN4 など
- ごく稀に下垂体腫瘍を合併する遺伝性疾患。
<下垂体性PRL分泌亢進症>の経過は?
🔹 1. 経過(進行の流れ)
① 初期
- 女性:月経不順・無月経・不妊・乳汁分泌が出やすい。
- 男性:性欲低下・勃起不全・不妊。
- 共通:軽度の頭痛、倦怠感。
👉 多くのケースでは、こうした症状が出た段階で血液検査→MRIにより診断される。
② 進行期
- 腫瘍が大きくなる(マクロ腺腫, >10mm)と:
- 頭痛や視野障害(特に両耳側半盲)。
- 下垂体全体が圧迫されると、**他のホルモン分泌低下(副腎皮質、甲状腺、性腺機能低下)**が出る。
- PRL高値のまま放置すると:
- 不妊の持続
- 骨粗鬆症の進行(エストロゲン・テストステロン低下のため)
- 性機能障害の固定化
③ 長期経過
- マイクロ腺腫は進行が遅く、薬物治療でコントロール可能なことが多い。
- マクロ腺腫は増大して再発もしやすいため、薬+手術+放射線の組み合わせで長期管理が必要。
- 適切に治療されれば 生命予後は良好。ただし未治療ではQOLが大きく低下する。
🔹 2. 予後に影響する因子
- 腫瘍の大きさ(マイクロ vs マクロ)。
- 治療への反応性(カベルゴリンなどドパミン作動薬に反応するか)。
- 視神経や下垂体機能への圧迫の有無。
- 薬剤性や二次性のPRL高値なら、原因を取り除けば速やかに改善。
<下垂体性PRL分泌亢進症>の治療法は?
🔹 基本方針
- 原因の大半は プロラクチノーマ(PRL産生下垂体腺腫)。
- 治療は「腫瘍の大きさ・症状の有無・妊娠希望の有無」に応じて選択されます。
🔹 1. 薬物療法(第一選択)
- ドパミン作動薬(カベルゴリン、ブロモクリプチン)
- ドパミンはPRL分泌を抑制するホルモン。
- これらの薬は PRL分泌を抑え、腫瘍を縮小させる効果がある。
- 多くの患者で効果があり、マイクロ腺腫なら9割以上がコントロール可能。
- 妊娠希望のある女性では、薬を調整しながら妊娠継続が可能。
🔹 2. 手術療法
- 適応:
- 薬が効かない・副作用が強い場合。
- 視神経圧迫などで視力障害が進行する場合。
- 方法:経蝶形骨洞手術(TSS) が標準。
- 成功率は腫瘍の大きさに依存(マイクロ腺腫は成功率高い、マクロ腺腫は再発しやすい)。
🔹 3. 放射線療法
- 手術後に再発した場合や、薬が効かない例で選択される。
- 効果発現まで数年かかることがあるため、薬物療法と併用されることが多い。
🔹 4. 薬剤性・二次性PRL高値の場合
- 原因薬剤を中止または変更。
- 甲状腺機能低下症 → 甲状腺ホルモン補充。
- 慢性腎不全 → 腎機能治療・透析。
<下垂体性PRL分泌亢進症>の日常生活の注意点
🔹 1. 生活全般での注意点
- 定期通院を守る
- プロラクチノーマのサイズやPRL値を定期的にチェック。
- 薬を自己判断で中断・減量しない。
- 症状の変化に敏感になる
- 視野が狭くなった、頭痛が増えた、月経が止まった、性欲が低下した…などの変化はすぐ報告。
🔹 2. 食生活
- 特別な制限は基本的に不要。
- ただし 骨粗鬆症リスク があるため、カルシウム・ビタミンDを意識した食事(牛乳、魚、きのこ類)。
- アルコール・カフェインの過剰摂取はホルモンバランスや睡眠に影響するので控えめに。
🔹 3. 運動
- 激しい制限は不要。
- ただし腫瘍が大きく視神経圧迫がある場合は、頭に強い負担をかける運動(重い筋トレ・格闘技など)は控える。
- 骨粗鬆症対策のために、ウォーキングや軽い筋トレは推奨。
🔹 4. 妊娠・出産を考えている場合(女性)
- 妊娠希望は早めに主治医へ相談。
- 妊娠中は腫瘍が大きくなる可能性があるため、妊娠中も視力や頭痛のチェックが重要。
- カベルゴリン・ブロモクリプチンは妊娠初期に中止されることが多いが、ケースによって調整。
🔹 5. 薬との付き合い方
- ドパミン作動薬は長期内服が基本。
- めまい・吐き気・血圧低下など副作用が出たらすぐ報告。
- 他の薬(抗うつ薬・制吐薬など)がPRL値を上げることがあるので、新しい薬を始めるときは必ず主治医に確認。
✅ まとめ
- 定期通院とホルモンチェックが最重要。
- 骨と心血管への影響を防ぐために、食生活と適度な運動を意識。
- 妊娠希望時は必ず主治医と相談。
- 薬の自己中断や他薬との飲み合わせには注意。